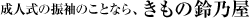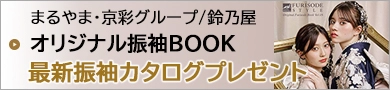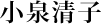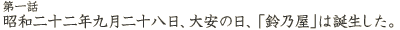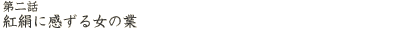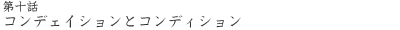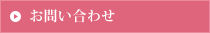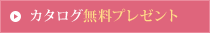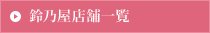清子の思ひで
私も姉について、週に一度ぐらいは大森へと顔を出す。上野からタクシーを拾うと、「ねえちゃん、どこへ行くんだい。五十銭でいくよ」と愛想がいい。「大森でもいィ?」、「おまけしとくよ」。不景気も底をつき、中年の運ちゃんは五十銭でも有難い風だった。空のタクシーが何台も並んで、客待ちをしていた。
母は決して大森に足を向けなかった、最初から料亭は反対だったようだ。「この不景気に二足のわらじをお父さんは穿くようになったけど、絶対にうまくいかないと思う。しかし、やり始めたからには、本業がおろそかになったら大変だ。私がしっかりここを守らなければ・・・・・。」と、それからの母は必死の面持で店頭に立ち、大勢の番頭たちの意思統一に懸命だった。
時々、大森に手伝いに出かけていた姉は、一時は元気をとり戻したが、やはり具合が悪いらしく、次第に寝つく日が多くなった。弟も同じように、咳をしはじめた。このまま東京にいては、病気は進むばかり。やがて、空気のいい千葉の郊外に家を借りて、姉と弟は転地療養の身となる。姉の目が届かなくなった会計は、やがて使い込みが発生し、素人で始めた料亭は三年も続かないで閉店となった。その負担が、不景気で思わしくない本業にもろに響いていく。一度下りはじめると、止めようもなかった。
毎年何枚も着物を別染めしたり、呉服店、百貨店と歩きまわって買い物をしていた母は、ピタリと中止して、わずかに盆と暮に、店の人のお仕着せを買い揃えるだけとなった。
私は学校から帰るとすぐ制服をぬぎ、着物に着替えた。新調は望めないので、小学校の頃にたくさん作ってあった銘仙や米流(よねりゅう)の着物を洗い張りして、四つ身から本裁に仕立て直したものである。着物にはそういう方便がある。
えんじと黒で織りなした市松模様の秩父銘仙がふだん着には一番着心地がよかった。帯はへこ帯を結んだ。足袋は別珍。えんじ色であった。
あの頃の日本は?


上野公園で大礼記念国産振興東京博覧会開かれる。
アムステルダムオリンピック800m競走で、人見絹枝が日本女子初の銀メダリストに。