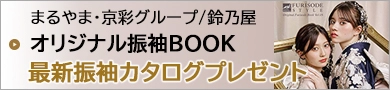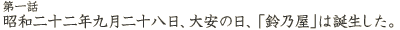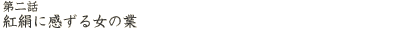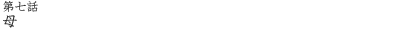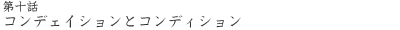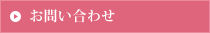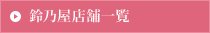清子の思ひで
 図書館通いを続ける一方、夜は夜でかなり遅くまで机に向かった。
学校の成績も一年ごとによくなって、四年生になってからは、クラスでも10番以内に入っていた。乙は英語と音楽だけの時があった。
図書館通いを続ける一方、夜は夜でかなり遅くまで机に向かった。
学校の成績も一年ごとによくなって、四年生になってからは、クラスでも10番以内に入っていた。乙は英語と音楽だけの時があった。
小学校時代のような全甲は、恐らく一組に一人いるかいないか、とにかく五年になったらクラスで三番ぐらいになってみたかった。級中何番というのは、最終学年にはっきり通信簿に書いてあった。
いよいよ目標の師範の試験が近づいてきた。「あなたはやせているから、第二次の体格検査だけがちょっと心配よ」と担任の山口先生にいわれた。たしかに、クラス中で一番体重が少なかった。30キロそこそこぐらいで、やせて貧弱だった。父はそれをきいて心配しはじめた。「よし、良いことがある」。
翌日、早速自製の腹巻きを作らせた。そしてその中に一銭銅貨をつめるだけつめ込んでお腹に巻き、その上を黒いズロースでかぶせた。当時はみな黒い下穿きをつけていた。体重を計るにも下穿きをとらずに計ったものだ。一銭銅貨の重みも加わって大分体重も増して、父は「しめた」といって喜んだ。父の苦心のアイデアであった。
入学式当日の朝はいつもに似ず緊張した。長い間の目標だったし、現在の家庭の事情から最善と信じて、ここ一校しか受験しなかった。何としても入学しなければ、という神経の昂ぶりがあった。第一日目の最初が、数学であった。緊張の余りばかに難しく考えてしまい、一番自信のあった数学だけに、どうして解けないのか気ばかり焦る。焦れば焦るほどわからなくなってしまい、とうとう10の問題ともできず白紙で出す始末。あとから思えばすごくやさしい問題だったのだ。
国語や化学、歴史は順調にいった。それでも第一次は通ったが、第二次の結果、やはり不合格であった。父の腹巻きの協力も無駄の終わった。私はなす術を知らず、空虚と焦燥と、自己嫌悪に胸かきむしる思いだった。父は、「女子大に行け」とさかんにすすめた。「月謝のことなど心配するな」と口にこそ出さないが、目は語っていた。これ以上、親に心配はかけたくない。はっきり決心すると、私は早速翌日学校の事務局へ行き就職のことを申し出た。